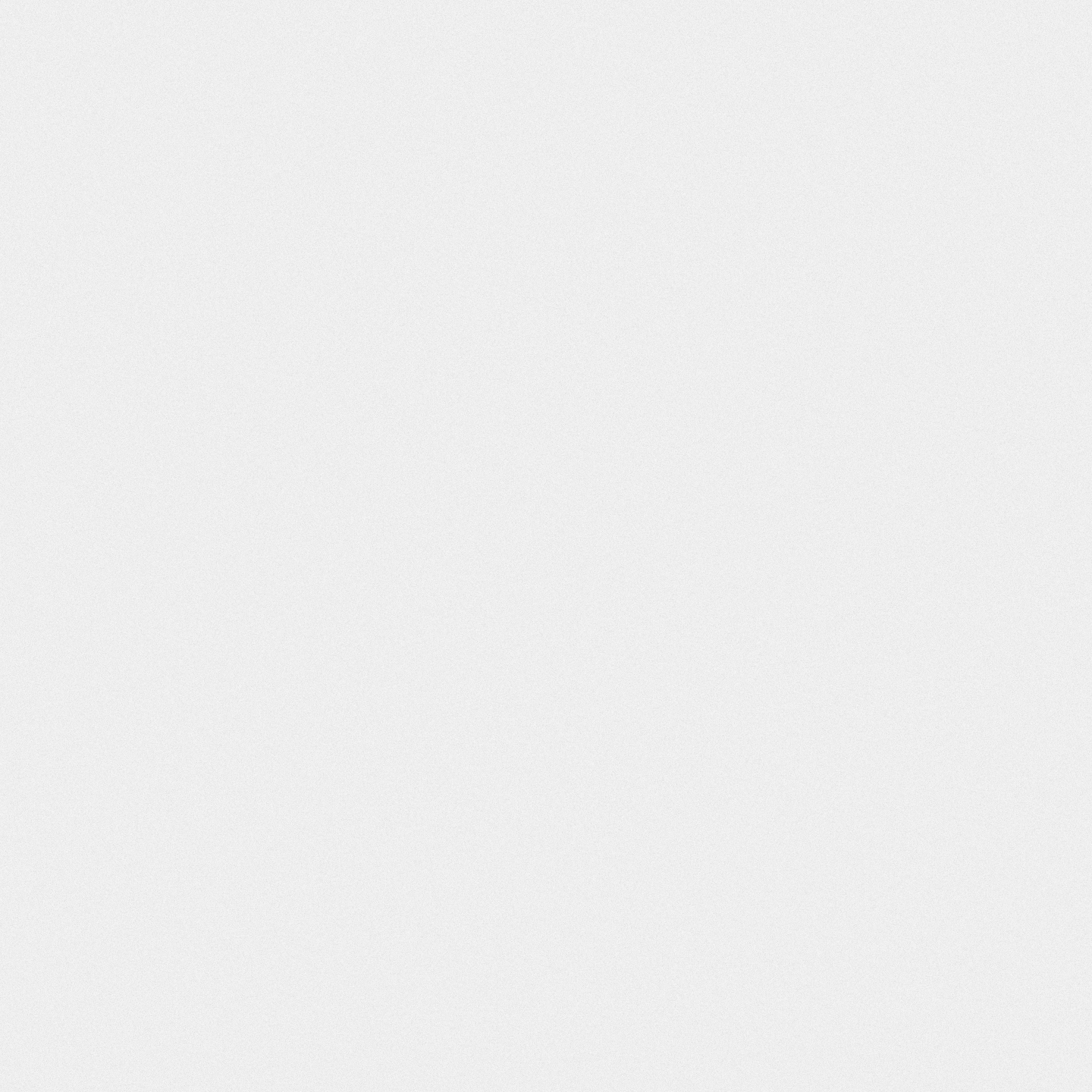チーズの香りがする味噌は妥協をゆるさぬ木曽職人の贈り物-Part1

日本人にとって欠かすことのできない調味料の一つが味噌。大豆と塩と糀が基本材料となる味噌には、米味噌、豆味噌、麦味噌と大きく分けて3種類ある。米味噌の場合は、米に糀菌を繁殖させ米糀を作る。それに茹でた大豆と塩とを混ぜ、寝かせてじっくり醸造させ出来上がってくる。
昔はそれぞれの地域や家庭で作っていたほど、種類は様々で豊富。「家の数ほど味噌がある」と言われた時代もあった。「手前味噌」という言葉は、現代では「自慢する」という意味で使われるが、もともとは、「自分で作った味噌が一番おいしい」と自分の作った味噌を褒めることに由来している。

今でも味噌は数えきれないほど種類は多い。その中で、長野県木曽郡、中山道近くに位置する小さな糀屋さんの味噌が際立った個性を発揮している。手造りにこだわったこの味噌は、フレッシュチーズのような香りがするのだ。お味噌汁にすると、具を入れなくても、出汁と味噌だけで十分なくらい味は濃厚。しっかりとした発酵による旨味もしっかり出ている。お椀の最後の2~3口は、なぜか花畑の甘いフローラルな匂いに包まれる。見た目からは想像できないこんな芳香が、なぜこの味噌から漂ってくるのだろう?
木曽の山あいの小さな工房
本州のほぼ中央に位置する長野県。長野県の旧名「信州」というと、全国的にも味噌の生産地として有名で、伝統的に味噌の生産量や消費量が多い県だ。大手味噌メーカーもいくつもある。2014年には全国の味噌生産量のほぼ半分を占めて*1いたし、同年と翌2015年には年間一人当たり味噌消費量で第一位のポジションを占めている。直近の2017年でも一人当り消費量は全国第3位*2だ。そもそも味噌好きの県なのだ。

同県南西部の小さな村で1879年以来、140年にわたり味噌屋さんを営んできた小池糀店。今でこそ、このチーズの香りがする美味しい天然醸造味噌と、手造り米糀をふんだんに使った自然な甘みの甘酒が人気を博しているのだが、ここに至るまでの道のりは決して単純ではなかった。

小池糀店は約30年前、木曽長福島の町長夫人だった唐沢美貴さんが経営していた。自身の高齢化と子供たちも別の仕事をしていたことから店の経営は傾く一方だった。ちょうどその頃、同じ地域に住む現在の経営者、上村三枝子さんの夫である昇さんが以前から味噌屋を経営してみたいという夢を持っていいたことから、小池糀店は上村さんが買い取った。その後、昇さんは店の経営にも慣れ安定してきていた。しかしその頃、体調を崩し入退院を繰り返すようになり、1998年、昇さんは他界してしまった。
妻の三枝子さんには親から継いだ会社の経営もあり、小池糀店だけに集中することが許されない状況だった。味噌屋を継ぐ人はおらず、三枝子さんは創業140年の歴史ある店を絶やしていいものかと逡巡し、困惑していた。そんな時、小さな奇跡が起こった。
元の経営者の唐沢さんには4人の孫がいた。全員男子で千葉県流山に一家で暮らしていた。この孫の両親、つまり美貴さんの長男夫婦が、子どもの1人を木曽のこの店に送り出すというのだ。長男夫婦は、自身の親が糀店の経営に行き詰まった時に、上村さん夫婦に助けられたという感謝の気持ちを持ち続けており、今度は自分たちが助けたいと三男の尚之さん木曽に送り出すという。二人は、味噌づくりの経験がない尚之さんを新潟の味噌蔵へ修行に出した。
血のつながった親の実家とはいえ、再び閉店の危機にさらされている小池糀店に息子を送り出してくれた長男夫婦の気持ちに応え、一時は店をたたもうかとさえ思っていた三枝子さんの気持ちが少しずつ前を向き始めた。それまで何十年も小池糀店で働いてきてくれたスタッフの助けも経営者としての覚悟を後押ししてくれる大きな力になった。
余暇はパチンコ兄弟から音楽兄弟、そして味噌兄弟へ
尚之さんは千葉での仕事を辞め、全く異なる世界に飛び込むことを決意した。こうして1998年5月、27歳で尚之さんは流山を後にし、木曽の小池糀店に住み込むことになった。冬には厳しい寒さが訪れる山岳地帯に切り開かれた小さな村。美しい昔の町並みが残るこの村で、尚之さんの新しい人生が始まった。
するとその一年後、四男の裕之さんも大学をやめ小池糀店に住み込み、兄と共に働き始めた。しかし当時の資金繰りは非常に厳しく、夏の間、裕之さんはアルバイトをしなければならかった。そんな時でも、夜になると皆で集まり、三枝子さんの作った料理を食べながら冗談を言い合い、笑いは絶えなかったという。
とはいえ、全く異なる生活に飛び込んだ二人の心の負担は軽くはなかった。木曽に友達がいない淋しさを紛らしたり、仕事のストレスを発散するために、二人は空いた時間にパチンコ通いを始める。三枝子さんは、十分とは言えない給料をこの兄弟がパチンコに掛けてしまうのをやきもきしながら、方向転換させる方策を考えていた。

「当時は『やってられねーな』と思ったし、ほんとにやめたいと思ったことは何度もあります。しかし、パートさんの雇用や事業者どうしの付き合いもあり、やめたくてもそう簡単にはやめられなかったんです」と兄の尚之さんは言う。「この小さな事業者としての田舎の『しがらみ』がいい意味で今まで続けさせてもらえる力になりました。」
仕事が終わるとパチンコ通い、という二人の生活を変えたきっかけは音楽だった。実は、尚之さんと裕之さんは、子どもの頃からクラシック音楽に親しんで育った。合唱指導者だった彼らの父親は、オーケストラの指揮者もつとめていた。尚之さんはオーボエとピアノ、裕之さんはバイオリンというようにそれぞれ得意とする楽器があり、木曽に移り住んだ際、二人とも自分たちの楽器と共にやって来たのだった。

二人がパチンコ通いをしていた当時、三枝子さんの友人からの要望が発端となり、この地域で30人ほどの女性コーラスグループが結成された。そのグループに、尚之さんはピアノ伴奏者、裕之さんは指揮者となって参加し、唐沢兄弟の音楽活動が始まった。音楽を通して活躍する機会が増え、町との交流も次第に深まっていった。
二人のエネルギーは、見事にパチンコから音楽へ。気づいたころには、数年間つづいていた閉塞感を突破していた。同時に、二人は亡き祖父母に導かれるように、糀や味噌づくりに没頭していった。「最初の10年はマイナス状態から安定路線に乗せるので精いっぱいでした。けれども、次第に世の中が発酵食品に関心を持つようになったり、甘酒の認知が向上したりなど、追い風が吹いてきました」と尚之さんは振り返る。「努力だけで会社がよくなったわけではありません。味噌屋としていい味のものを作り続ける覚悟はもちろんありましたが、そこに世の中が糀や発酵食品を見直す、という現象が起こり、事業を押し上げてくれたことも事実です。」
努力の先に吹いてきた追い風
2011年、全国的に塩こうじブームが起こった。米糀と塩と水を混ぜて数日間かき混ぜておくと実にまろやかな塩味の調味料ができる。肉にも魚にも野菜にも合う万能性、そして手軽さと健康効果からも、塩こうじは瞬く間に日本の一般家庭に広まった。この頃「糀」の存在がクローズアップされ始め、健康ブームに乗って、発酵食品への関心は一層高まった。

このブーム以前は、小池糀店は糀の販売に特に注力していなかった。しかし、この塩こうじブームの流れで、地元の百貨店などから糀を卸してほしいという要請が舞い込んできた。
取引が始まると、それまで他社の糀を使っていた顧客が小池糀店の糀を使い始めた。明らかに違いがあった。大量生産の糀と手造りの糀は味も質も決定的に違う。この違いに気づいた顧客がファンとなり、増え続け、百貨店や生協などへの出荷が急増した。この頃、小池糀店の売上は安定モードから成長モードへと移行した。三枝子さんが経営を断念しなければならないかもしれないと途方に暮れてから10年以上が経っていた。

糀は発酵食品の基本だ。その糀を使う食品のもう一つのブームに甘酒がある。甘酒というと、日本酒の粕から作られたアルコール飲料もある。ここでいう甘酒とは、米糀を発酵により糖化分解して天然の甘みを引き出したノンアルコール飲料「甘糀」のことである。
実は糀から作ったノンアルコール甘酒の方が歴史は古く、江戸時代に滋養強壮剤として売り出されていたという記録もあるくらいだ。一方、アルコール系の甘酒は明治~大正時代に作られた比較的新しい飲み物。長い間忘れられていた、数百年もの歴史を持つ昔ながらの甘酒は、アミノ酸やビタミンB群、ブドウ糖など点滴に含まれる栄養分を豊富に含んでいることから、美容と健康によい効果をもたらす「飲む点滴」といわれ、ここ数年で一気にスターダムに駆け上った。甘酒ブームはいまだに健全だ。統計によると、2017年時点で甘酒の市場規模は過去5年で4倍*3にまで増えている。
小池糀店の復活に大きく貢献した商品のもう一つがこの甘酒だった。糀の力を見るためにも甘酒を作ってはいたが、商品化はしていなかった。味噌蔵に寝かせてある何トンもの味噌の取引先を必死で探していたある日、東京に住んでいる三枝子さんの友達から「自然食の会社に小池糀店の味噌を卸してもらえないか」といわれ、早速その会社に電話してみた。味噌の見本と見積りを送る際、ちょうど横にあった甘酒を『皆さまでお召し上がりください』と一筆添えて箱に入れた。すると翌日この会社から、「甘酒をお取り引きします」と電話があり、最初の注文が1000個入った。「ああ、これでやっていける!」と三枝子さんの心に光が差し込んだ。
菌を「鍛える」、妥協しない米糀づくり

味噌でも甘酒でも多くの発酵食品の基盤になっているのは米糀作り。これがとにかく肝心なのだ。山の斜面を掘り込んだ洞窟のような空間に位置する小池糀店の室(むろ)は、夏は涼しく、冬は寒い。マイナス15度の極寒でもストーブ一個で室温を25度までに上げることができる。
糀の発酵には厳格な温度管理が必要だ。この地形を利用した糀室で、米糀作りはすべて手作業で行われる。通常、糀は蒸した米に種麹を混ぜ、慎重に温度を見ながら、72時間くらいかけて菌を繁殖させる。米の周りに満遍なく綿帽子の花が咲いたような状態になると完成だ。
違いを生み出すのは、米糀の「育て方」。小池糀店の方法は、菌に対して「厳しい」。繁殖の工程で糀菌を甘やかさないのだ。自分の力で繁殖するよう菌の自主性を鍛える。鍛えて強い糀を作るのは高い糖度を実現するためだ。だから、発酵の過程で一旦上がった温度を下げて、10時間くらい一定の温度で保ち、敢えて菌が自分の力で広がるのを待つ。
「自然発酵で、菌に自分の力をつけさせたいからです。早めに温室に入れてしまうと弱い糀になります。過保護にせず、厳しい環境下に置いて自力で繁殖させます。待ちながら叱咤激励するのです」と尚之さんは言う。もちろん待つ前の段階で、蒸した米に満遍なく菌が付着していることが大前提だ。小池糀店では人間の目でしっかり見ながら、手を使って丁寧に、均等に菌を蒸米につけていく。「1粒1粒の米に同等に菌が繁殖する状態にしたいので機械ではやりません。ベルトコンベヤだと、どうしても不均等さが出てきます。すると、まだ十分に繁殖していない部分まで一緒に冷ます工程に送り出さざるを得なくなります」と尚之さん。

大量生産の糀では、この不均等さが免れない。十分に菌がついていない部分まで糖化の工程に進むため、でんぷんの分解は弱く糖度が低くなる。すると甘味が少なくなってしまう。このような「弱い」米糀を使った甘酒には、甘味を加えるためにグラニュー糖を添加しなければならなくなるケースもある。
しかし、元気いっぱいに育った小池糀店の米糀を使った甘酒は、完全無添加で、味も自然糖化の甘さだけだ。じっくり待った分、とてもに甘い。いい糀を使うかどうかで甘酒の味も風味も全く変わる。ちなみに、小池糀店の甘酒は完成までに15時間かけている。甘やかされていない「強い糀」を使えば、15時間という長い自然発酵のプロセスでも雑菌は繁殖せず、その結果、臭みも色も出ない。唐沢兄弟は、すべての商品の基盤となる米糀作りでは、決して妥協しない頑固な職人と化していた。
こんなに入念に作られた米糀が使われている天然醸造の味噌。美味しさの秘密はやはりこの「強い」米糀なのだろうか? 2016年のある調査によると、朝食を摂る日本人の内、ご飯よりパンを食べる人の方が多いし、味噌よりヨーグルトを消費する人の方が多い*4という。日本人のソウルフードと言っても過言ではない味噌汁なのに、ここしばらくパンやヨーグルトの人気に負けている。
けれども、「ほんのりチーズとフローラルの甘い香りがする味噌」となったら、「濃厚で体に染みわたるような味わいがある味噌」となったら、しかも「天然醸造の味噌には健康効果がたくさんあるらしい」となったら、あえてこのチーズの香りのするお味噌を食べてみたくはならないだろうか? 小池糀店のユニークな味噌の魅力の正体は何か? その製法も教えてもらいつつ、Part2でご紹介する。
(Part 2に続く)

糀マイスター推奨🌸
小池糀店の商品はこちらから購入できます>>http://www.koji-miso.com/
(糀かねのねショップでは扱っておりません、ごめんなさい🙇)
写真提供:小池糀店
Text: Diane
-------------------------------------------------------------------------------------
*1:長野経済研究所2017年6月28日/
http://www.neri.or.jp/www/contents/1498621374919/index.html
*2:地域の入れ物/https://region-case.com/rank-h28-miso/
*3:Money Plus 2017年12月27日/https://moneyforward.com/media/life/48009/
*4:(株)マーシュ「朝食に関するアンケート」2016年2月実施/
https://www.marsh-research.co.jp/mini_research/mr201603choushoku.html